先日アップしたクリス・ロビンソン・インタビューに先立って行われた、クリス・ロビンソンによる山村浩二インタビューの一部の様子をお伝えします。2010年出版予定の日本のインディペンデント・アニメーションについての本のための取材です。
(通訳:上田もとめ、取材協力:国際交流基金)

『カフカ 田舎医者』(2007) (C) Yamamura Animation / SHOCHIKU
クリス・ロビンソン
『田舎医者』のプロジェクトについてですが、かなり以前から構想はあったんですか。
山村浩二
カフカの小説自体は、僕が20代の頃から読んでいました。『田舎医者』もそのときに。実際にこのプロジェクトが始まったのは2005年の夏で、それから一年半かけて、2007年の3月に制作が終わりました。
ロビンソン
なぜ『田舎医者』をアニメーションにしようと思ったんですか。
山村
いくつか理由ときっかけがあるんですけど。カフカは僕の好きな作家で、何度も読んでいたんですが、そのなかでも『田舎医者』は短篇の中で非常に完成度が高いと思ってたんですね。カフカにしては内容がリッチで――キャラクターやシチュエーションがいろいろ出てくるし――ある意味エンタテインメントだなと思ったんです。それで、アニメーションにしたら面白いんじゃないかと漠然とは思っていたんですけど。ユーリー・ノルシュテインと『頭山』について少し話をしていたときに、彼が、僕のスタイルとカフカがすごく合うんじゃないか、って言ったんです。
ロビンソン
カフカはピョートル・ドゥマウァがコピーライトをもっているようなものですね。
山村
彼は『フランツ・カフカ』という作品もあって、イメージとしてすごく強いですね。もちろん、キャロライン・リーフも『変身』を作ってますが。何人かはカフカに挑戦していて……ドゥマウァは数少ない成功例だと思うけど、リーフはカフカのイメージという面からすると、必ずしも成功していると思えない。アニメーションとしては素晴らしいですけど。『カフカ田舎医者』の最大のタイミングは、松竹という制作会社から、「なにか作りたいものはないか」という話が2005年にあったことです。そのときにパッと思いついたのが、カフカの『田舎医者』だった。最初は松竹から違うオファーがあったんです。ベストセラーの絵本を長編にしないか、というオファーだった。でもそれは興味がない原作だったし、長編で監督だけやるっていう事も興味がなかった。で、何度かディスカッションしていって、カフカに落ち着いていった。
ロビンソン
『田舎医者』も長編みたいですけどね。
山村
僕の中では非常に長いですからね。
ロビンソン
フェスティバルでかかる作品の中でも長い方ですし、作品の深みから考えても、いわゆる長編にふさわしい肉付けがしてあります。何度もメールで申し上げましたが、本当に素晴らしい作品です。数年に一回、頭にパンチを食らったような印象的な作品に出会うんですが、去年のアヌシーで観た『カフカ田舎医者』はまさしくそんな作品でした。観ている間、こんな感じでした。(口をあんぐりと開ける。)ペトロフの作品[『春のめざめ』]を観た苦しみを吹き飛ばしてくれました(笑)。ペトロフはオタワにはエントリーしなかったですね。お互いの間に暗黙の了解があるんですね(笑)。
話を戻しましょう。『田舎医者』はキャラクターが伸び縮みしますが、そのアイディアはどこからきたんでしょう。
山村
それはもう原作を読んだときから。人物の伸び縮みというのは作品に直接書かれているわけではないんですけど、時間の伸び縮みを原作からはすごく感じました。すごくアニメーションにフィットしそうだと。ヴィジュアルのイメージというよりは、伸びたり縮んだりという感覚を原作からは受けたんです。基本的には医者の一人語りなんですね。彼の気分も一瞬で変わるんです。笑っていたと思ったら、次の瞬間には怒っていたり。そんな精神の変化を、ヴィジュアルに置き換えたいっていうアイディアがあったんです。そして、原作からイメージスケッチをしているときに、医者の特徴的なポーズ――伸びたり縮んだり――が最初の段階から出てきました。
ロビンソン
悪夢のような感覚がありますね。夢の中の動きです。
山村
そうですね。足を前に出そうとしているのに、思うように動かないような。そういう独特の感覚、もどかしさみたいなものは出したいなと思っていました。僕自身も、このアイディアのおかげで、すごく自由に楽しんで作れたというところもあります。
ロビンソン
小説の中のどんな部分に惹かれましたか。人物でしょうか。
山村
いくつかありますけど、まず主人公の医者。彼の行動は他力本願。自分自身の意志があるようで、実はまわりに翻弄されたまま生きている。運命に逆らえない医者の感じが、人間の人生を象徴しているように感じました。他にも、唐突に始まる合唱だとか。二頭の馬の共演だとか。非常に面白い要素が多かったです。
ロビンソン
目の下の白い斑点がありますね。それが映像ではすごく効果的でした。そのアイディアはどこから。
山村
僕の幾つかのドローイングのなかで、そういう目の光の表現、目のつるっとした質感を表現するために、白いインクを入れました。『頭山』でもやっていたと思います。今回はとても目立ったのかもしれないですね。

『カフカ 田舎医者』(2007) (C) Yamamura Animation / SHOCHIKU
ロビンソン
今は何をなさっていますか。
山村
今はまだ準備中で、短篇の制作には取りかかってないです。でもカフカの後に一本短いものを制作しました。観ますか? 今年のオタワにエントリするつもりではありますが。
ロビンソン
じゃあ今審査すれば時間の節約になりますね(笑)。
(『こどもの形而上学』上映)
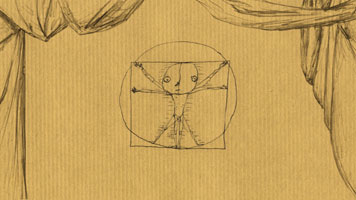
『こどもの形而上学』(2007) (C) Yamamura Animation
ロビンソン
『頭山』を作ってから、非常に脂がのってきていると感じます。ピークが来ていると。自分でもそう思いますか。
山村
えー、確かに……
ロビンソン
自信がかなりついてきているように思います。
山村
そうですね。『頭山』を完成させられたのがとても良かったと思います。それまでは自分のすべてを出し切れていないもどかしさ――もちろん技術も足りなかったんでしょうが――を感じていました。最近は自分の作りたい気持ちとテクニックのバランスが非常によく取れていると思います。
ロビンソン
『頭山』は非常に大きな成功を収めましたね。オスカーにノミネートされたり。同じような方向性でいこうという誘惑はなかったのですか。
山村
ないですね。いくつか作りたいイメージがあったので……『年をとった鰐』も『頭山』の前にアイディアがありましたし。自分自身の作品のコピーをつくりはじめたら、作家は終わりだと思いますので。常に次の表現、やりたいことを見つけていきたいと思います。でも、次とかその次くらいから苦しくなってくるかもしれませんね(笑)。まだやりたいことはいっぱいありますけど。
『こどもの形而上学』ですが、これは2006年の「IMAGE PAR IMAGE」という映画祭のポスターを依頼されたとき、子ども向けの映画祭だったので、子どもをたくさん使ったイラストを書いたんですが、自分でもそれが気に入っていて、子どもが出てくるアニメーションをいつか作ろうと思ってたくさんスケッチをしていました。具体的にフィルムにするとまでは考えてなかったんですけど。ちょうど『田舎医者』が終わって、これもいくつかのタイミングが重なって……これはあまり面白い理由じゃないと思うんですけど、ハーヴァード大学から学生が夏に研修に来たんですね。ルース・リングフォードの生徒なんですが。その学生に仕事を与えないといけなかったんですよ。それで彼にずっとこの作品のスキャンを手伝ってもらいました。そしたらできあがったんです(笑)。
ロビンソン
重たい作品を作ってらっしゃいますが、子どもにも楽しめるものに戻ってきたわけですね。これは子どもでも楽しめますよね? 怖がりますかね?
山村
たぶん大丈夫だと思います(笑)。カフカは怖いかもしれませんね。『こどもの形而上学』は、特に子ども向けという意識はなかったですが、気晴らしになりました。ある意味、軽く楽しく作れた良さは出てると思います。いろいろな作り方はあるかな、と思ってます。
ロビンソン
賞を貰うことに満足感はありますか。表層的なものではありますが。
山村
もちろんあります。やはり、取れなかったら寂しいです(笑)。どのへんが気に入らなかったのかなあ、とか思います。
ロビンソン
『頭山』がオタワで何も賞を取らなかったときにもですね(笑)。
山村
(笑)。あれが『頭山』の最初のコンペティションだったんです。でもだいたいそのジンクスがあって、『田舎医者』の最初のコンペティションがアヌシーで、やっぱり賞を取れなかった。
ロビンソン
アヌシーにとってはクレイジーな作品でしたね。アヌシーは[スージー・テンプルトンの]『ピーターと狼』みたいな大人しい作品が好きですから。これからの予定はどうでしょう。長編制作に興味はありますか。みなそちらの方にいきたがるようですが。
山村
基本的には考えてないですね。まず何を作りたいかというのが先にあって、それに合わせた長さが作れるから短篇はいいんですね。3分でも20分でもいい。だから、最初に目標の分数をなるべく定めないで作るようにしてます。もちろん、漠然とは考えますけど。だから、今後やりたいものに長いものに適したものがあれば、当然長編を作ると思うんですけど。もしかすると長編になってしまうかもな、というアイディアも一つあります。でも、今はそれを作ろうというところまで固まっていないです。
ロビンソン
CMはまだやっていますか。
山村
去年の12月にテレビコマーシャルを仕上げました。
ロビンソン
オファーは多くなってますか?
山村
そうでもないですね。なんとなく、僕は自分のやりたいスタイルしかやらないというのが伝わっているみたいで。だから、僕がやりたいと思うものだけがくるという感じで、それはすごくハッピーなんですけど。なるべくそこにたくさん時間が割きたくないので。短篇を作る機会を増やしていきたいです。
ロビンソン
一般の観客からの感想を聞く機会はありますか。ラブレターとか。
山村
ラブレターは来ないですけど(笑)、今ちょうど『田舎医者』の劇場公開をしているんですね。レイトショーですけど、一般の映画館で。ブログなんかチェックすると、感想が結構あります。だいたい大きく分かれますね。ものすごく良いと思ってくれる人と、まったくわからないという人。多くの人はストーリーというところでつまづくみたいです。
ロビンソン
イゴール・コヴァリョフにインタビューしたときに言っていたのは、「観客は混乱したままに放置しておくのが一番いいんだ」と。良い意味での混乱ですが。でも、多くの人は困惑するのを嫌いますね。すべてをはっきりさせてほしいと思うらしい。
これはどの作家にも質問していることなのですが、短篇アニメーションは広い意味での一般大衆に触れるものではありません。それはフラストレーションになりますか。
山村
幸いなことに、僕は一般上映の可能性に恵まれています。『頭山』のときも、『鰐』のときも、カフカもそうでした。だからある意味での満足は得られています。でも、まったく一般に知られない立場にある他のアニメーション作家の人たちの気持ちはすごくわかるし、僕も長い間そうだった。多くの作品はフェスティバルでしかみれないわけですよね。でも、僕自身、そういったフェスティバルでしか観れないような作品に影響を受けてやってきたわけです。だから、僕自身が作っていく上での目標としては、一般に受けるよりも、より素晴らしい作品を作っていきたい、一般には理解されなくても、良いものを作りたい、と思っています。
2008年1月24日 ヤマムラアニメーションにて
