<今年の特別プログラムについて>
・パノラマ
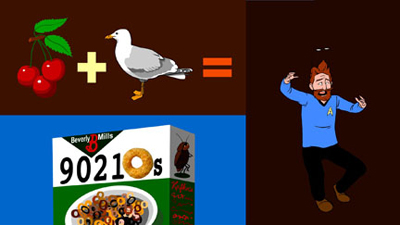

Missed Aches、『晴れ ときどき 曇り』
Missed Aches(Joanna Priestley) はベテラン作家プリーストリーの新作で、スペルミスを放置しておいた文章をそのまま映像化していくコメディー作品。当然のことながら英語がきちんと分かっていないと笑えないが、テンポよく展開していくアニメーションを観ているだけで充分楽しい。
『晴れ ときどき 曇り』Partly Cloudy(Peter Sohn)は『カールじいさんの空飛ぶ家』UP併映のピクサーによる短編アニメーション作品。こういったフェスティバルで(しかもパノラマ・プログラムで)数多くの作品と並んで鑑賞すると、改めてその異質さが際立つ。なんたる高水準。(褒め言葉では必ずしもない。)コウノトリが赤ん坊を運んでくるという伝承に基づいた内容で、作品全編に漂う多幸感はディズニーの「シリー・シンフォニー」シリーズを思わせる。ピクサーはこの時代のディズニーと並ぶくらいの円熟期に入っているのではないかと思わず考えてしまう。ああ、偉大なる嘘。
・The Stereolab at the NFB: Exploring Three Dimensions
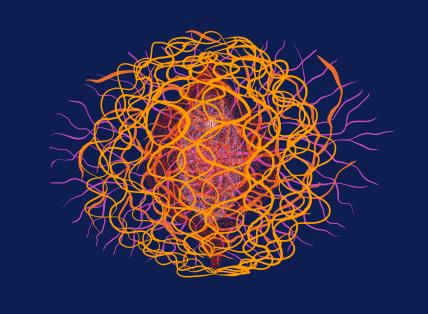

June、Drux Flux
穏やかでゆったりとした空中浮遊感覚を味わわせてくれるFalling in Love Again(2003、Munro Ferguson) は、内容自体は他愛もないものだが、それが逆に、メディアの新奇性へと関心を集中させてくれ、メディア初期特有の熱量も感じることができた。
June(こちらも2003、Munro Ferguson) は抽象アニメーションを3Dで観るとこんなに新鮮なのかという驚きを与えてくれる。抽象アニメーションなので表象的な立体空間など当然存在するはずもなく、空間は純粋に創造されていく。
セオドア・ウシェフのTower Bawher (2006) とDrux Flux(2008) も3D化されて上映されていたが、あらかじめ3D化が想定されていた後者の方が断然に興味深い出来となっていた。3D化することによって情報量が格段に増し、イメージが重層的でゴージャスに。段違いの迫力だった。
・Seven Reasons to Love Animation
今年のオタワの名誉会長オットー・アルダーによるセレクト・プログラム。上映作品を並べれば、『クルテク もぐらくんとズボン』(1957、ズデニェク・ミレル)、『話の話』(1979、ユーリー・ノルシュテイン) 、『色彩幻想 過去のつまらぬ気がかり』(1949、ノーマン・マクラレン)、『78回転』(1985、ジョルジュ・シュヴィッツゲーベル)、『バランス』(1989、ウォルフガング&クリストフ・ロイエンシュタイン) 、『フィルム、フィルム、フィルム』(1968、フョードル・ヒトルーク)、『櫛』(1986、ブラザーズ・クエイ)。他のプログラムが当然のことながら現代に偏るなか、こういう「クラシックな」作品に浸れるプログラムは非常に貴重。
海外の映画祭に参加すると、観客の反応のダイレクトさに驚かされるが、ここオタワはアヌシーほどではないにせよ(アヌシーの観客は時おり暴走しすぎて不快)、やはり笑えるところには素直に笑う。『話の話』を日本以外で観るのはそういえば初めての経験だったのだけれども、例えば少年がカラスにリンゴを食べさせる場面やオオカミの子がジャガイモを熱がる場面で結構な量の笑いが起こる。そうだ、思い出した、ノルシュテイン作品にはユーモアがあるんだ、ということを改めて確認することができた。(ダンスのシーンで恋人たちが引き離されていく場面で笑いが起きたのはどうかと思ったが。)それぞれのシーンが喚起させる情動の振れ幅がこの作品ではとても重要なのだということを、海外の観客と観ることで実感することができた。ユーモラスなシーンとシリアスなシーンのモンタージュ。不吉な魚と「永遠」の穏やかさ。会場自体も基本的に静寂と緊張感を漂わせ、とても良い雰囲気だった。
・In the Dust and Moonlight of Don Hertzfeldt(ドン・ハーツフェルト・レトロスペクティブ)
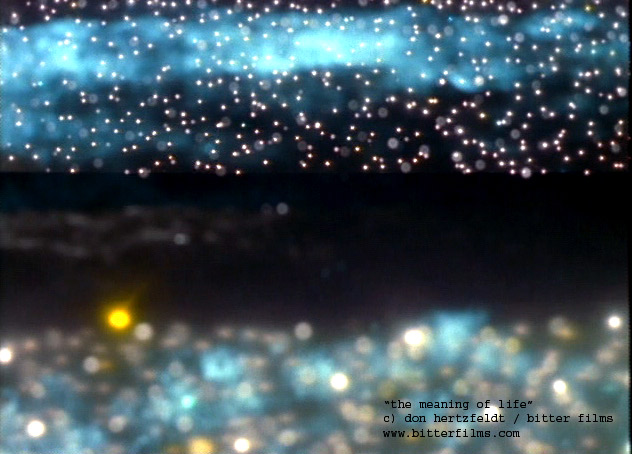

The Meaning of Life、I am so proud of you
彼の作品をいくつか通して観ると分かるのは、彼のタイミング操作技術の適切さ。後のトークセッションでは「ビートを大事にしているので何度も何度も編集はやりなおす」と言っていたが、ワーナーの黄金期を支えたチャック・ジョーンズやテックス・エイヴリーらが、一コマタイミングが異なるだけで笑えるものも笑えなくなるといった旨の発言を残しているのを思い出した。(ただしハーツフェルト自身はワーナーのカートゥーンについては「古く感じる」と否定的だけれども。)今回のトークでは他にもモンティ・パイソンやチャーリー・チャップリンへの言及があり、彼のサイレント映画およびコメディ好きの側面を確認させてくれることになったわけだが、サプライズとして上映された新作カートゥーン(タイトルは明かされなかった)はまさにそんな彼の真骨頂。親知らずを抜くというただそれだけのことなのに、ハーツフェルトの代名詞といっていい長回し(特別なことが起こったわけではないのに、突如として「何かが変わった」と感じとってしまう不思議さ)と動作の始動のタイミングの巧妙さが観客をぐっと引きつける。それゆえにスプラッター的な場面が効いてくる。観客が痛みを共有し、絶叫が起こるわけだ。
彼のブラック・コメディ作品は、笑えると同時に残酷でもある。今回北米での上映に参加してみて、Billy’s Balloonが一番人気であることがよくわかったが、個人的にはこの作品はとても笑えるものではない。ハーツフェルトがこの作品を笑わせようと思って作っているとはとても思えない。Everything Will Be OKとI am so proud of youという近年のヘビーな作品群もその両面性は変わらない。膨大な量の情報量がこれでもかとばかりに畳み掛けられてくるこれらの作品を構成するどのエピソードも、哀しい可笑しさとでもいえそうなものを感じさせる。彼のマッチ棒型のキャラクターは、本来あるべき情報の欠如によって、観客の想像力による補完を要求することとなるが、それと同様に、これらの一見なんてことないエピソードは観客にプラスアルファの感情を喚起する。彼が観客との対話を重視するのも、そういった観客との馴れ合いに陥ることのないキャッチボールが彼にとって重要だからではないかと思わせた。
アニメーションは観客の想像力を最も削減してしまう危険性をもったメディアだが、たとえばオットー・アルダーのセレクトした作品だとか、ハーツフェルトの作品には、そうではない、逆に観客に想像力喚起の無限の可能性を与えるポテンシャルがあることを感じる。作品を観ているときに全身が感じる感触が明らかに違うのだ。
フェスティバル体験が素晴らしいのは、半ば強制的に好きな作品もそうでない作品も見せられつづけるがゆえに、もう何度も観たことがある作品もまた、他の作品や会場の雰囲気とのモンタージュによって新たな姿を見せてくれることだ。今年のオタワはメイン会場がバイタウンシネマという映画館だったことも素晴らしかった。映画を見せるために作られている会場でアニメーションを観るというのは実はあまりない体験なのだ。短編アニメーションは特にパソコンの小さなスクリーンでひどい画質で自分の気が向いた作品を観ることがほとんどになりつつある現状、大画面大音量で無差別に作品に晒されるフェスティバル体験というのはとても貴重かつ重要だ。
![]()
公式サイト:オタワ国際アニメーションフェスティバル
関連記事(1):「ドン・ハーツフェルト インタビュー」
関連記事(2):デイヴィッド・オライリー「アニメーション基礎美学」